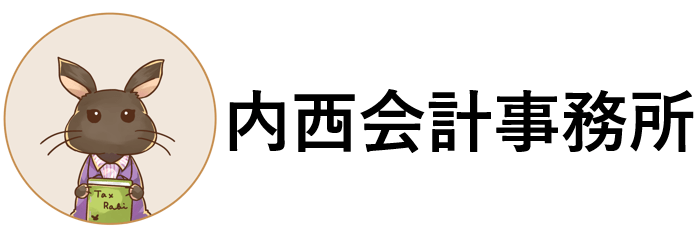2024年税制改正~退職金課税の長期勤務の場合の税優遇の見直し改正案見送り
こんにちは。
和歌山市の女性税理士、内西です。
10月下旬、朝夕が肌寒くなってきたと思っていたら、
11月に入るなり季節外れの暖かい日が続いています。
早朝は暖房があった方がいいかなと思うのに、昼間は車中クーラーをかけることもあるこの頃。
扇風機が出たままなのにそばにホットカーペット。
なんだかよく分からない季節です。
さて、国会では連日2024年度税制改正の議論が行われています。
マスコミにも取り上げられている所得税、住民税の定額減税。
一人あたり所得税3万円と住民税1万円、合わせて4万円。
たとえば、世帯主と配偶者、子供二人の世帯では、合わせて16万円の減税。
時期は来年6月頃実施を目指しているようです。
今回の改正案には減税が多く、
今年の6月に経済対策案として挙げられていた、
退職金課税の見直し(増税)
は見送られることになったようです。
当事務所メニュー一覧
プロフィール
電話での税務相談~30分(NEW)
オンライン税務相談
メールでの税務相談
法人成りの手続きのサポート(NEW)
ひとり社長(マイクロ)法人の決算申告(NEW)
オンライン(対面可)での記帳指導
税務調査立ち会い(個人事業主限定)
税務顧問・個人のお客様
税務顧問・法人のお客様
現行の退職金課税について
退職金課税は、
他の所得とは分けて計算する分離課税で、
長期間働いた労をねぎらい、
勤務期間が長ければ長いほど税金がお得になる課税方法です。
算式 退職所得=(退職金―退職所得控除額※)×1/2
※退職所得控除額・・・勤続年数20年以下 勤続年数×40万円(最低80万円)
勤続年数20年超 800万円+(勤続年数―20年)×70万円
勤続年数の1年未満の端数は切り上げ
例:退職金900万円
勤務期間
①15年
②21年
退職所得はいくらになるか?
①900万円―(15年×40万円=600万円)=300万円
300万円×1/2=150万円・・・退職所得
②900万円―{800万円+(21年−20年)70万円}=30万円
30万円×1/2=15万円・・・退職所得
このように同じ退職金でも、
勤続年数の長さで課税される金額が135万円も変わってきます。
①②の金額が所得の場合、
これらの所得に所得税等5.105% 住民税10%がかかってきます。
終身雇用を前提とした制度
この課税制度は終身雇用を前提とした制度で、
早期に退職すると税金的に不利になります。
本当は退職したくても、
このように税金の負担が増えることを考えると思いとどまる風潮があるため、
労働移動がすすまないとの指摘がありました。
一方退職金を分割して年金形式で受け取る場合には、
公的年金等に区分され公的年金等控除の対象となります。
この場合勤続年数によってかかる税金には差がありません。
よって、労働移動を促進するためにも、
この退職金課税を年金形式で受け取る場合の課税方法に一体化する改正案が出ています。
思うこと
結果的にこの改正案は増税になるため、
2024年度税制改正では見送られましたが、
近い将来改正が入る見込みです。
改正後、退職を控えていた人の早期退職が進むでしょうが、
改正前に現行の退職金課税を当てにして、
長期勤務していた役員やサラリーマンの駆け込み退職が、
一気に進むのではと思います。
(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできませんのでご了承ください。
また、記事の内容は、記事更新日現在の法律に基づいたものになります。現行の法律と異なることがあることをご了承ください。
当事務所メニュー一覧
プロフィール
電話での税務相談~30分(NEW)
オンライン税務相談
メールでの税務相談
法人成りの手続きのサポート(NEW)
ひとり社長(マイクロ)法人の決算申告(NEW)
オンライン(対面可)での記帳指導
税務調査立ち会い(個人事業主限定)
税務顧問・個人のお客様
税務顧問・法人のお客様
メール相談承っております
メール相談
オンラインでの記帳指導をさせていただいております(会計ソフト導入のサポートもさせていただいております)
インボイス制度についてのご相談はこちら(小規模事業者限定)
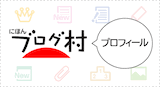
ライン公式アカウントでもこの税金ブログを配信しています!!
👇👇
クリックして頂けるととても嬉しいです!!
↓ ↓ ↓